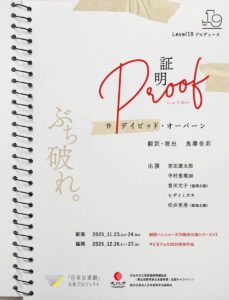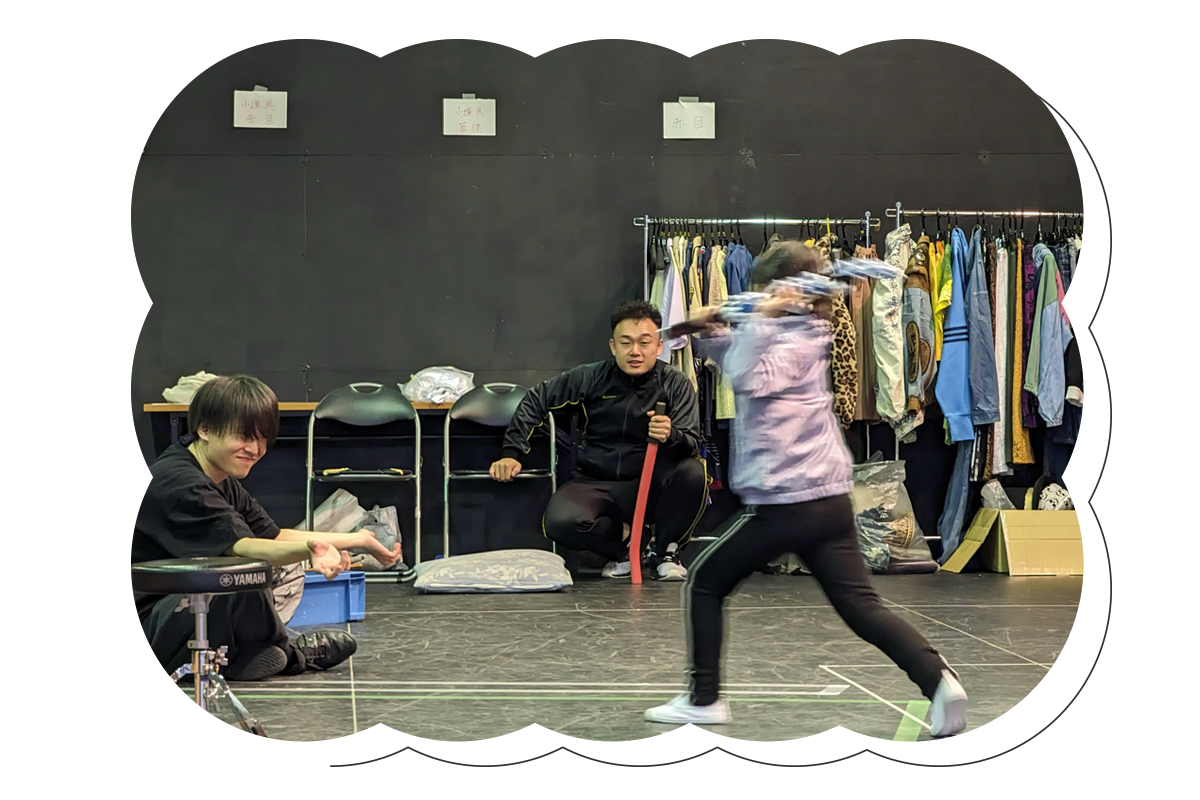声を上げて!黙って聞くから
なぜ「善意」は「配慮」にならないのか? 黒澤世莉
目次
話を聞こう、企画の前に
意思決定の場に「当事者」がいること
そもそも、どういう企画であれば子育て中でも参加できる演劇ができるんだ?
その答えを知っているのは、子育て中の当事者です。
考えるまでもなく当たり前のことですが、その当たり前がなぜかなかなか思いつかない。意識の外にあることというのは、なかなか意識に上らないものです。
それまでは、企画サイドで従来通りのスケジュールを決めて、出演者やスタッフに共有していました。それではいけない、今まで通りになってしまう。
だから、子育て中の関係者に、参加可能なスケジュールを考えてもらうことにしました。
「夜間は厳しい」
「オンラインツールを活用してほしい」
「対面リハーサルは参加したいから、家族の都合がつく日にしてほしい」
などなど。中には矛盾した意見も出ましたが、それも当たり前です。子育て中であっても、それぞれの状況は全部違うのですから。
実際の要望を聞くことで、対応しなくてはいけないこと、対応できないこと、意外と問題のないこと、などが整理されていきました。
その中で見えてきたのは、小さな声が大きな仕組みを変える力になるということ。
ある子育て中の俳優は言いました。
「『私なんかが言っていいのかな』って遠慮しがちだったけど、言葉にしなきゃ何も伝わらない。それを『ワガママ』と思わずに発信していいんだって思えた」
この姿勢が、ゆっくりとですが座組に浸透していくのだと思います。
当事者が発信することで、非当事者も「自分が気づいていなかった」ことに気づいていきます。
そして「これは子育ての話に限らない」ということにたどり着きます。
稽古時間、移動、情報共有の仕方などなど。
そのひとつひとつの事情を確認して、希望を聞いて、仕組みを見直す。
それは、遠距離に住んでいる方、ダブルワークの方、その他事情がある方々、そして特に問題を抱えていない人まで、全員にとって働きやすい環境をつくることにつながっていきます。
勇気を出して声を上げよう
互いに歩み寄るための具体的なアクション
子育て中の当事者の方にも、非当事者の方にも提案があります。
子育て中のあなたへ
勇気をもって声を上げてください。
あなたが困っていることは「自分勝手な言い訳」ではなく、「環境改善への提案」です。
「これを言ったら迷惑かな」と思う気持ちはよく分かります。
でも、あなたの言葉を聞いて初めて、周囲の人は自分の想像の外側にある当事者の世界を知ることができるのです。
その声は、未来の誰かを助ける道標になるかもしれません。
非当事者のあなたへ
相手が話し終わるまで、黙って聞いてください。
子育て中の方は「自分の都合で周りに迷惑をかけている」という意識があり、自分の意見を飲み込む傾向があります。
もし話をしてくれたら、まずは黙って最後まで聞いてください。途中で遮っては、気持ちを折ることになりかねません。
そして、話を聞いたら「それは大変だね」で終わらせるのではなく、「どんな希望がある?」と聞いて、何ができるか一緒に話し合ってみてください。
当事者の希望を現実に変える力を持っているのは、多くの場合、非当事者の側です。
歩み寄りは、どちらか一方の努力では成立しません。
「話す」「聞く」「対話する」このステップを踏んでから、ようやく本当の意味での「配慮」が生まれます。
演劇の現場での試行錯誤は、きっと社会の縮図でもあります。
一人ひとりの小さな行動が、その場の当たり前を変えていく。
その始まりは、たった一人が切り出した「困っていることがある」という言葉と、それに応じた一人の「聞くよ」というやりとりなのかもしれません。
おわりに
子育てと演劇が両立できる現場をつくりたいと思いつつ、私は多くの失敗をしてきました。
その過程で、他者を傷つけたことも一度や二度ではないと思います。悪意がなくても、たとえ善意であっても、当事者についての理解が浅いと相手を傷つけてしまうことがあります。そこには反省が必要です。
この記事を読んでいるあなたには、同じ轍を踏んでほしくありません。
当事者と非当事者の対話が始まると、すべての問題が解決するか? というと、もちろんそんなことはありません。むしろこれはスタートです。
対話から課題が顕在化して、配慮すべき点が見えてきます。しかし、すべての点を配慮することは不可能です。それは、当事者と非当事者の間だけでなく、当事者同士であっても利害が異なる場合があるからです。
それでも、対話がない場合よりはるかにマシです。
今の私の考えでは、全員の100%ハッピーは無理でも、80%なら可能だと考えています。どの80%を選ぶのか? それが対話の役割なのだと思います。
もちろん、これから変わっていくかもしれません。
これからも対話を続けていく中で、新たな気づきが得られることでしょう。
もっといい方法が思いついたら、またシェアしたいと思います。
互いの声を聴き、仕組みを変え、環境を整えていく。
うまくいかなかったことは止めてみる。
その積み重ねが、誰にとっても活動しやすい稽古場への道になっていくのではないでしょうか。
いま子育てをしていなくても、いつかは子育てをするかもしれない。
当事者と非当事者の境界は、いつだって入れ替わるものです。
だからこそ、合理的な配慮は「他人のため」ではなく、「自分のため」にも必要なのです。
あなたが今日話し出すことが、あるいは時間を取って話を聞くことが、遠慮をやめることが。
明日の現場に配慮が増えて、誰にとっても活動しやすい現場が増える、その一歩になるかもしれません。
今回はここで終わります。最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
公演情報
Level19プロデュース
『証明』
作:デイビッド・オーバーン
演出・翻訳:黒澤世莉
福岡公演@塩原音楽・演劇練習場 大練習室
⇒2025年12⽉26⽇(金)、27⽇(土)